以前、司書教諭の資格を取って学校図書館の活用がマイブームだったころに書いた文章が出てきました。2006年ごろの少年写真新聞社「図書館教育ニュース」のポスターと一緒についてくる先生用の資料に書いた「なつかしの国語の教科書」というタイトルの原稿です。あの頃は図書館に熱かったな…。
なつかしの国語の教科書
突然ですが、今、大人の皆さんに質問です。
小学校の時の国語の教科書に、どんな文章が載っていたでしょうか?もう何十年も前のことになるので、パッとは出てこないと思います。だけど、同年代の人に「昔、国語の教科書にこういう話なかった?」と簡単なストーリーを聞かれて「あ、そういえば…」と、意外に思い出せるものです。タイトルや固有名詞は忘れても、挿し絵や最後の一文などを断片的ながらも詳細に覚えていたりすることは多いです。
今回は、昔の小学校の国語の教科書に載っていた作品の中から、現在でも入手可能なものを紹介していきたいと思います。もちろん、世代や教科書会社によって思い出の作品は当然違ってくきますが、今の子どもたちにも、子どもの頃読まずに大人になった方にも読んでもらいたい本を選びました。(※ネタバレ注意!)
「アニメーションとわたし」(手塚治虫)
子どもの頃からアニメーションにとりつかれたこと、ディズニー映画にとりつかれ、仲間とアニメーションを作り上げたという漫画家・手塚治虫の書き下ろしエッセイ。
この作品にいたく感銘を受け、手塚少年のまねをして、教科書やノートのすみを利用してパラパラマンガを描きまくって先生に怒られたのでは私だけの話とはとても思えません。きっと全国にたくさんいるでしょう。しかし、この文章を読んでアニメーションの魅力にとりつかれた小学生にそれをするなと言うのは、どだい無理な話です。まさに『禁じられた遊び』!そういう意味では、たいへん罪作りな作品ではあります。「光村ライブラリー (17) 「わたし」とはだれか」(光村図書出版)に掲載されています。
 |
新品価格 |
![]()
「かわいそうなぞう」(土家由岐雄)
戦争のため上野動物園では象を殺さなくてはいけなくなりました。毒薬の入ったえさを与えても食べず、毒薬の注射も針が折れてしまいます。しかたなくえさをあげずに飢え死にさせるしかありません。動物園の人たちの苦悩の中、ついに鼻を長く伸ばして万歳の芸当をしたまま、死んでしまいます…。
もうこれは、まるで催涙ガスでも浴びたかのように泣けます。毎年毎年8月15日に秋山ちえ子さんがラジオで朗読されたというのもうなづけます。「かわいそうなぞう」というタイトルのまま金の星社から絵本が出ています。
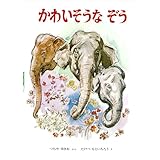 |
新品価格 |
![]()
「田中正造」(上笙一郎)
足尾銅山の鉱毒事件に果敢に戦った田中正造の伝記です。
議会で熱く訴えますが、政府や企業の対応は解決にはほど遠く、状況は悪くなる一方。ついには議員を辞して明治天皇に直訴を試みますがそれも失敗してしまいます。最後まで戦い続けましたが志半ばにこの世を去ってしまいます。
「やっぱり伝記といえば田中正造だよね!」という人も少なくないのではないでしょうか。それくらいインパクトがあった作品です。特に死後に身よりのものがずた袋を開けてみたら、聖書一冊とと日記三冊と小石と少しの鼻紙だった、というラストは、私利私欲を捨てて住民のために戦った偉い人だな~と子供心に圧巻。だから伝記といえば田中正造なのですね。「光村ライブラリー (16) 田中正造」(光村図書出版)に掲載されています。
 |
新品価格 |
![]()
「おしゃれな牛」(木村静枝)
小さな駅の新人駅員・昭さんの帽子が、通過した貨物列車の風で飛ばされてしまいます。後日、昭さんが高原に行ってみると、その帽子をかぶった牛に会います。その牛は帽子を取ろうとすると怒って抵抗する、おしゃれ牛なのでした…。
今読み返してみると、昭さんの行動がずいぶん子どもっぽいという気もするのですが、それはさておき、ウイスキーのCMで一世を風靡した、柳原良平さんの挿し絵がとても印象的です。「新・心にのこる 3年生の読みもの」(学校図書)に掲載されています。
 |
新品価格 |
![]()
「最後の授業」(アルフォンス・ドーデ)
フランツ少年がその日も遅刻して学校に着いてみると、どうも様子がおかしい。実は戦争でフランスが負けたため、今日はフランス語で授業をする最後の日だった。退職するアメル先生も熱弁をふるい、宿題を忘れて恥じたフランツ少年も真剣に授業を受け、最後に先生はフランス語への熱い想いを述べ、黒板に大きな字で力強く「フランスばんざい!」と書いて、学校を後にする。
これも感動的な作品で、3社の国語の教科書に掲載されていましたが、1985年を最後に一斉に教科書から消えてしまいました。この舞台となったアルザス地方は、フランス語ではなく、むしろドイツ語(の方言?)が使われており、現実はこの作品の状況と大きく異なっていたはずだ、そんな設定にしたのは作者がフランスのナショナリズムの向上のためにこの作品を書いたからではないか-という指摘があったことが原因のようです。だとすると、あの感動は誤解によるものなのでしょうか?いや、生徒や地域の人たちの先生に対する、あるいは先生のフランス語(ひいては学問)に対する熱い想いは歴史的事実の誤りをカバーしてありあまるものと思いたいのですが…一教師としては。「最後の授業」(ポプラ社文庫―世界の名作文庫)などに掲載されています。
「すなの中に消えたたんねさん」(乙骨淑子)
発明家の電気屋、たんねさんは店に子どもたちを呼んだりして楽しく暮らしていました。ある日、たんねさんは悩み事を砂に変える空色のせんたく機を発明して、みんなの悩みを解決します。ところが、そのためにかえってたんねさん自身は辛くなってしまいます。子どもたちの心配も届かず、たんねさんはついに自ら空色のせんたく機を使い、大量の砂を吐き出してロボットになってしまいました…。
今回の原稿を書こうと思ったきっかけは、ズバリこの作品との再会があったからです。小学生だけに読ませるにはもったいないです。むしろ、ストレスをためこんだ、それこそ「空色のせんたく機」がほしい現代人にぜひ読んで、さらにたんねさんに思いっきり感情移入して、とどめにラストの二文で泣いてもらいたいお話です。ただし、この作品が教科書に登場したのは、昭和52年度から54年度に使われていた学校図書の4年生下巻だけのようです。したがって「小学校のとき『たんねさん』を読んだ」というと、年齢がかなり特定されてしまいますからご注意を。「読んでおきたい4年生の読みもの」(学校図書)に掲載されています。
-懐かしい1冊、ありましたでしょうか。残念ながら知っている作品がなかった方も、どうぞ、あのころ読んだ教科書とあのころの自分を思い出してみてください。
今回は意外に現在も出版されていたものが多かったです。光村ライブラリーとか心に残る●年生の読み物とか、教科書に載った本をまとめた本は教科書に採用されなくなってからも国語の先生に一定の需要があるんですかね。だったら「最後の授業」も「たんねさん」も残してほしかった。とくに『たんねさん』は大人に刺さる児童文学としてもっと評価されるべき(確信)。



コメント