有性生殖では、2個体の親から、遺伝子を半分ずつもらうのですが、両親からもらう遺伝子の組み合わせはたくさんあり、それゆえ、親との子を比べると形質が違いますし、同じ両親からできた子どうしの形質を比べても、どこか違いがみられることがむしろ自然でしょう。
特に親子に注目すると、親と子の形質はちょっと違う、その子が親になって作った子の形質はさらに違う、そしてその子の形質は…と難題も積み重ねていくとやがては「ちょっとの違い」とは言えないレベルに違ってくることもありそうです。
このように長い世代(長い時間)の流れで、過去にいた生物が多様な変化(進化)を遂げていき、現存している多様な生物につながっているわけです。生命すげー。
ということで、ここで「利己的な遺伝子」置いておきますね。もう40年経つのか。
ちなみに、私が「利己的な遺伝子」を知ったのは、ちょうど大学時代、真田広之が高校の生物の先生役をやっていたドラマがあって、彼の愛読書がこの本だったんだよね。ちなみにビーカーをカップにしてコーヒー飲んでた。一応言っておくけど、このドラマの影響を受けて教師になったわけではないぞ。
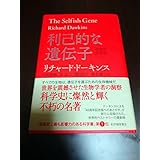 |
新品価格 |
![]()
 |
高校教師 Blu─ray BOX(1993年版) [Blu-ray] 新品価格 |
![]()
中学理科でいわれている多様性は、世間一般でいわれている「生物多様性」を意味していると思ってたら、結構肩透かしを食らうかもしれません。単に、共通性・多様性の視点という理科の見方・考え方によるものといった方がいい気がします。いろんな種類の生物がいる(多様性)けど、みんなこんな特徴がある(共通性)みたいな感じでしょうか。たとえば子房を利用する被子植物もいれば、利用しない裸子植物もいる(多様性)けど、みんな種子を作りたい(共通性)とか。
ぶっちゃけ今回は書く内容がなかった。


コメント