そもそも分類とは
分類そのものについては図書館情報学なんかで詳しく扱われています。そういえば、その昔、私は若気の至りで「司書教諭」と「司書」の資格を取ってしまった前科があります。そのときに「分類」そのものについて詳しくやったな~としみじみと。
そう思いながら情報検索していくと
緑川信之、「分類をみつめなおす:区分原理に注目して」『情報の科学と技術』 2016年 66巻 6号 p.254-259, doi:10.18919/jkg.66.6_254, 情報科学技術協会
という論文にぶち当たりました。
それによると、
「分類」は
(1)対象を分けること(区分),
(2)分けられた対象を体系的に配置すること(体系化),
(3)特定の対象を分類体系の中に位置づけること(分類作業),
(4)分類体系の特定の項目に位置づけられている対象を取り出すこと(検索)
の4つの段階に分けることができるのだそうです。
これが業界のスタンダードなのか、この人が勝手に言っているだけなのかは判断がつきませんが、ただ、「なるほど、たしかにそうだ」という感じがするので、これを今回の拠り所にします。
従来はマニュアルに従って分類するだけだった
すると、図書館の本を日本十進分類表で分類することとか、物質を有機物と無機物に分けることとか、ごみを分別することとかは、分類の4つの段階でいえば、(3)特定の対象を分類体系の中に位置づけること(分類作業),にあたるものです。
また、「○○の仲間にはどんなものがあるか」みたいな例示、さらには、「山手線ゲーム」なんかは(4)分類体系の特定の項目に位置づけられている対象を取り出すこと(検索)といえます。
これらはすでにある体系にもどづいてどーのこーのしているわけで、「思考」というよりは「技能」に近い。だから、これを仕事にしているとAIにうばわれて失業しちゃうよ、という話は前回したところです。
今度は「分類マニュアルを作る」という作業が入る
ところが、新しく中学理科でやる「生物の特徴と分類の仕方」は、それとは違います。わざわざ解説に「学問としての生物の系統分類を理解させることではないことに留意する。」とかかれているように、日本十進分類表に基づいて、『授業をもっと面白くする! 中学校理科の雑談ネタ40』という本を375.42理科教育に分類するようなノリで、アブラナを植物-種子植物-被子植物-双子葉類-離弁花と分類することを目指しているのではありません。
ここでやろうとしているのは、 分類するための観点を選び,基準を設定することと指導要領の解説にあるように、(1)対象を分けること(区分),(2)分けられた対象を体系的に配置すること(体系化),の領域の話なのです。
すでに決まった体系に具体例を当てはめていくのと異なり、区分し、体系化していくことは、答えが唯一絶対というわけではありません。特に生物の場合、「特徴」といっても色々な観点でみることができ、どのような観点で区分していくかというところは、その区分や体系化が有用であるかかどうかは別として、多種多様なものが考えられます。だから分類の観点や基準を変えると、分類の結果が変わってくるというような、1つの分類法に従って分類するだけでは決して見出すこともなかった知見が得られたわけです。
何万冊の本と本棚を前に、「この本棚にはこんな本を入れよう」とジャンルを考える、もっというとオリジナル日本十進分類表を作る作業です。これは大変クリエイティブな、AIにはちょっと苦手な作業かもしれません。
おそらく中学1年生を対象とした授業では、生物を分類してみて、どうしてそのように分類したかを話し合ったり発表したりすることになるのではないかと思います。
そこに分類表の三つの要素について触れてみるのはありなのかもしれません。生徒が分類する前に紹介するか分類した後に、生徒が行った分類を例に説明するかは先生のお考えや生徒の実態に応じて検討していく必要があるかと思いますが。
で、分類表の三つの要素とは? 長くなったのでまた今度。
おまけ:ところでこの記事のタイトル、「君たちはどう分けるか」の元ネタは、ご存じの方も多いかと思いますが、 吉野源三郎 『君たちはどう生きるか』(岩波書店) です。いいよね~。いちいち胸に刺さって出血多量になりそう。
 |
価格:1,430円 |
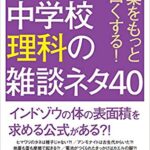

コメント