相違点は目立つし扱いやすいけれども、本質が隠されているのは共通点の方ではないか、という話を移行前のブログで初めて書いてから、もう7~8年もたちます。
学生時代のモヤモヤ
きっかけは「裸子植物」を指導していたときでした。被子植物を例に子房が果実に、胚珠が種子になることを学習してから、それはさておき…と、裸子植物について学習する。そして裸子植物の最後のところで被子植物と裸子植物の違いを定義づけて、これらを合わせて種子植物という(ドン!)というまとめ方にどうも違和感を感じていたのです。
もっというと学生時代の塾のアルバイトのときから、「被子植物=胚珠が子房に被われている、裸子植物=子房がなく胚珠がむき出し」と呪文のように覚える指導を見て、「それがここで本当に重要なところ(本質)なのだろうか」と疑問をもっていました。とはいえ、そこは入試に頻出とされるところなので、自分もY谷O塚に通っている小学生に呪文として暗記させていました。それが塾としての正しい指導ですから。
成果と課題
「直感は外れても、違和感は外れない」と言われます。その違和感をもち続けながら何度も「裸子植物」の授業をしていくうちに、生物にとって重要なのは子房の有無のような相違点ではなく、種子を作って仲間を増やすという共通点ではないか、ということを見出し、胚珠(種子)があればいいんだから、子房(果実)って、別にいらないんじゃね?という導入から「子房のない種子植物はあるのか?」という課題で裸子植物を扱う授業展開が、現在の自分のやり方として確立していますし、このような呪文の暗記よりも本質の理解を重視するという指導は、自分の理科教師としての矜持にもなっています。
それでもまだ自分の中で課題が残っていました。本質が隠されている、つまりより重要なのは共通点なのだけれども、よりピントの合った「共通点」を見い出ださせるにはどうはたらきかけたらよいか、という点です。酸素と二酸化炭素の共通点で、「空気より密度が大きい」とか「酸素原子を含む」などの答えが欲しいのに「気体である」ならまだしも、「物質である」という答えは、そりゃそうだけどピントがすれています。でもこのピントの合った答えを要求するのがなかなか難しいところです。AとB「だけ」の共通点をいかに生徒に忖度させずに適切な答えを出させるか、悩ましかったのです。
※比較の観点をこちらから提示するというのはすぐに思いつきますが、それをやると一気につまらなくなるので却下しています。
ダメダメの授業からの発見
その一つのヒントが、ある授業を拝見して見つかったのです。
そうするとさぞかし素晴らしい授業を見たのだろう、と思うかもしれませんね。それが全く逆で、どこから突っ込んでいいのかわからなくなるレベルでダメダメの授業でした。一応言っておくと、基本的に私は人の授業を悪く言わないことにしているのですが、そのポリシーを曲げざるを得ないような、いまだかつて見たことがなかった、ある意味斬新な授業でした。教室に入ったときにすでにあった板書をみて「あっ…(察し)」ではあったのですが、その悪寒を軽く凌駕する、一周回って清々しい授業でした。
詳しい授業内容の記述は避けますが、その授業をもとに私が気づいたこととして、2つだけの比較では相違点はみつけやすくても、ピントの合った共通点は見つけにくい、だから3つ以上のものをグループごとに分類することで、グループ間では相違点になるけれど、それぞれのグループ内ではピントのあった共通点(このグループだけに共通して、他のグループとは共通しない特徴)が容易に得られるということに気がついたのです。
そしてそれを具体的な方法としてまとめたのが、こちらの記事になります。
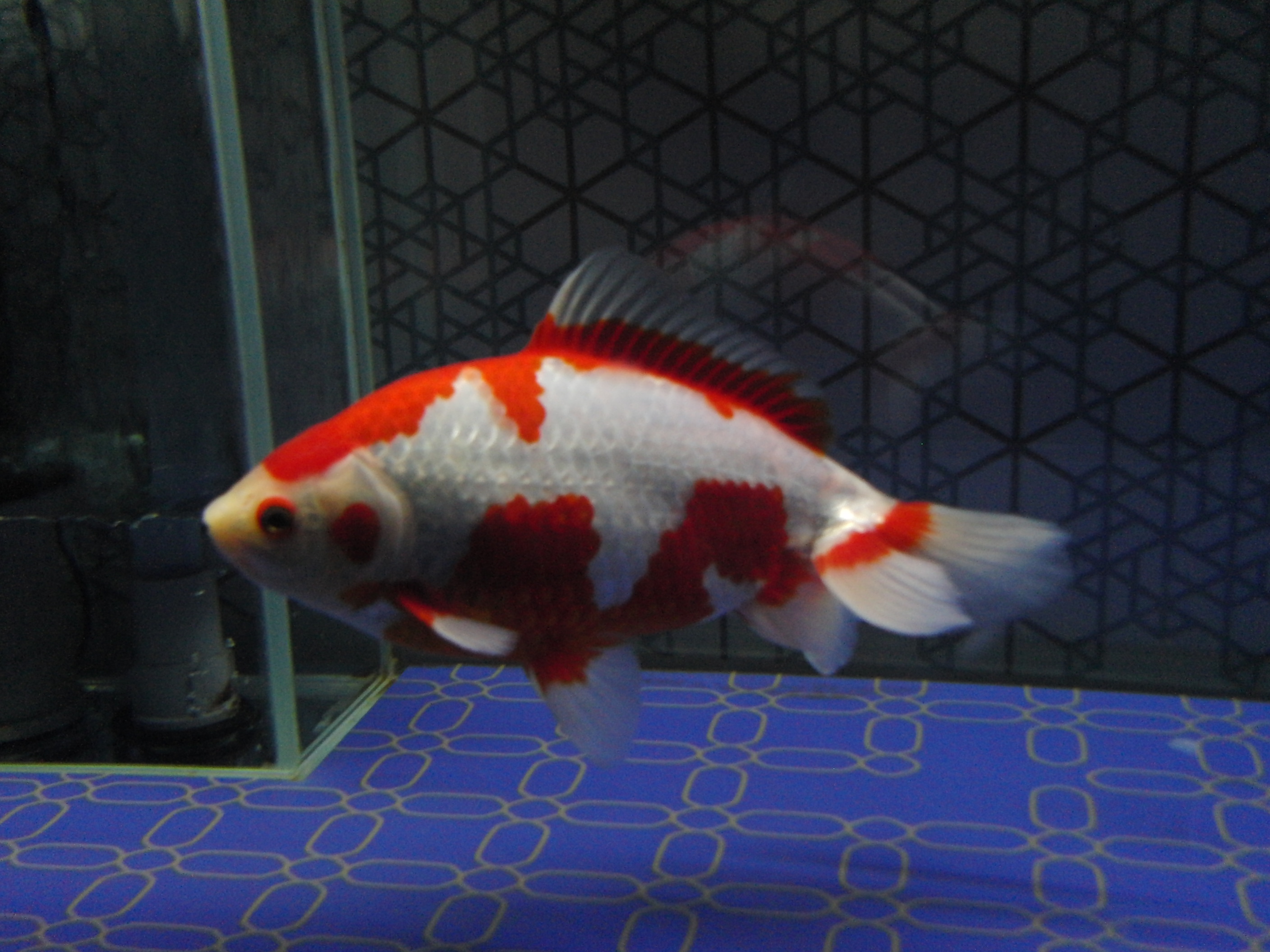

生物の特徴と分類の仕方の授業では、生物の特徴をもとに観点や基準を設定して分類していきます。このとき、理科の見方の一つである「共通性と多様性」由来の共通点と相違点がどうしても必要になってくる、という仕掛けなのですね。とくに共通点、それもピントの合った共通点はなかなかこれ以外の方法で取り上げにくいわけですから、観点や基準を設定して分類するという学習に大きな意義が見いだせるわけです。
ということで、(1)違い、(2)分類の4段階、(3)分類表の三つの要素 と3つまで書いたまではいいがその後が続かなかった「君たちはどう分けるか」というシリーズ、ようやく完結することができました。めでたしめでたし。
※続編が出ました。



コメント